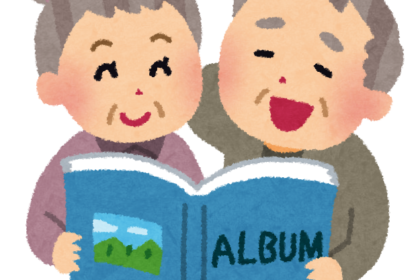高齢者の脱水症状をチェックする方法や予防策をご紹介!
高齢者の脱水症状は、気づかないうちに進行しやすいと言われています。
たとえ軽度の脱水症状でも、放置したままでいると命に関わる重篤な状態になり得るので要注意。
今回は、高齢者の脱水症状をテーマに、具体的な症状やリスク、そして高齢者が脱水症状を起こしやすい理由を解説。また、チェック方法や予防策についてもご紹介しますので、この夏にぜひご一読ください。
高齢者の脱水症状とは?
脱水症状とは具体的にどのような症状が出てしまうのか、そして放置するとどういったリスクが考えられるのかを以下で詳しく説明します。
脱水症状の具体例
脳の場合は頭痛・めまい・立ちくらみ・意識消失・けいれん、内臓は嘔吐・下痢・食欲不振、筋肉はこむら返り・しびれ・麻痺などが起きます。
症状の程度は下表の3段階に分かれます。
【軽度】
- 皮膚・口唇の乾燥
- ぼんやりする、うとうとする
- 食欲不振
- めまい、ふらつき
【中度】
- 頭痛
- 吐き気、嘔吐
- 下痢
【重度】
- 意識もうろう
- 失神
- けいれん
軽度の場合は水や経口補水液、中度の場合は経口補水液を飲ませましょう。
重度の場合は医療機関の即時受診が必要です。
脱水症状によるリスク
脱水症状で体液が減ると、酸素や栄養素が体内へ行き渡らずに血管や脳、内臓などが正しく機能しない状態となります。
気温上昇で発汗が多い場合、電解質が減るため血液濃度が上がって血管が詰まりやすくなり、気温低下で血管が収縮すると、夜間などに血液濃度が高まるでしょう。
脱水症状を放置して深刻な状態に陥ると、心筋梗塞や脳梗塞の発症リスクが高まり命に関わる危険性もあります。
高齢者が脱水症状になりやすい主な理由
まず、年齢や季節を問わず脱水症状は誰にでも発生するリスクがあります。
そして高齢者が脱水症状になりやすい主な理由には、次の4つが挙げられます。
-
体内水分量が少ない
体重あたりの体液の割合は小児80%、成人60%、高齢者50%で、加齢に伴い低減します。
筋肉量が減ると蓄積できる体液量も減少するでしょう。
食べ物や飲み物を口から胃へ送る機能の障害や、食欲不振などでも水分摂取量は少なくなりがちに。
-
暑さやのどの渇きに気づかない
高齢者は感覚機能の低下により、暑さを感じにくかったりのどの渇きに気づかなかったりする傾向があります。
その結果、体温調整がうまくいかずにエアコンを使用しないで脱水症状へつながるケースは珍しくありません。
-
排泄障害や糖尿病などの持病がある
糖尿病では増加した糖を排出するため尿量が多くなりがち。頻尿などの症状があると、体内の水分が過剰に排出されやすくなります。
また高血圧の治療に用いられる降圧剤を普段から服用する場合、利尿成分が含まれているため体内から塩分が減ることも原因に。
-
水分摂取を我慢しがち
高齢者自身がトイレに行くのを面倒に感じ、水分補給をあえて我慢する可能性もあるでしょう。
特に夜間のトイレ回数を減らしたいと思い、意図的に水分を控えた結果、脱水状態になるケースが多いようです。
脱水症状を簡単にチェックする4つの方法
実際に脱水症状を起こしているかをチェックするには、以下の6つの方法を取り入れてみるのがおすすめです。
高齢者だけでなく、誰でも簡単に確かめられる方法なのでぜひ参考にしてみてください。
-
手の爪を見る・手の甲をつまむ
手の指先は細い血管が集まっていて循環機能の変化を確認しやすい部位です。
親指の爪を逆の手の親指と人差し指でつまんで、指を離してピンク色に戻るのに3秒以上かかると脱水症状の可能性があります。
また、水分が不足すると皮膚が戻りづらくなります。手の甲をつまんだときに皮膚が3秒で元に戻らなければ要注意。
-
舌を見る
- 舌の表面が割れている
- 赤黒く乾いた状態
- 光沢がない
これらの様子が見られる場合、脱水症状を疑いましょう。
-
脇の下・手足の指先を触る
脇の下が乾燥していて湿気が無い場合、脱水症状の疑いがあります。
特に夏は、高齢者の脇の下が湿っているかを積極的にチェックしてみてください。
また、体内の水分量が足りないと、細い血管が集まる手足の指先は血行不良で冷たくなります。
指先を触って冷たい時は注意が必要です。
-
尿の色を見る
水分量が足りていて正常な場合、尿の色は薄い黄色です。
そして、体内水分が少ない場合は尿量が減り、色も濃くなる傾向に。軽度の脱水症状だと濃い黄色、中度は茶色、重度なら茶褐色へと変化します。
高齢者の脱水症状の予防策
最後に、高齢者の脱水症状の予防策についてまとめます。
高齢者本人が気をつけるだけでなく、できるだけ家族や周囲も協力しましょう。
時間を決めて水分摂取
定期的な水分補給を心がけますが、本人がのどの渇きを自覚できない場合は周囲から声かけをしましょう。
起床・毎食時・運動前後・入浴前後など時間を決めてこまめに水分摂取する習慣を作ると効果的です。
1日に摂取する水分量を意識
体重50kgの高齢者が1日に摂取すべき水分量は2ℓ程度と言われます。
換算すると体重1kgあたりの必要摂取量は約40㎖。食事から摂取する水分量が約1ℓ。残り1ℓ超を目安に水や飲料から摂取しましょう。
好みの飲料や果物を用意する
水は味気ないと感じ、喜んで飲んでくれないことがあります。高齢者が積極的に水分補給できるよう好みの飲み物を用意しましょう。ただしカフェインやアルコールは控えます。
また、果物は水分の宝庫。果物を食べるだけでおいしく楽に水分摂取できます。ゼリーや水ようかん等も、のど越しがよくおすすめですよ。
まとめ
水分不足などで、めまいや頭痛など様々な不調を引き起こすのが脱水症状。高齢者本人や周囲も気づかないまま放置すると、重症化して命に関わるリスクもあります。
今回ご紹介したチェック方法や予防策を参考に、できる限り健康な生活を維持できるような取り組みを心がけていきましょう。
東海市の東海レーベンは、日常的に対処しづらい高齢者の脱水症状など、様々な悩みで不安を抱える家族が安全に暮らせるようなサービスを日々提供しています。
ご相談はいつでも承っておりますので、まずはお気軽にご連絡をお待ちしていま